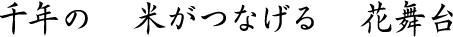日本酒の原料は米ですが、日本で稲作が始まる前にもお酒は造られておりました。日本で稲作が始まったのは一般的には縄文時代の終わりごろといわれております。稲作が始まる前のお酒の原料は、ぶどうやりんごなどの果実でした。果実に天然の酵母が付着して、アルコールが生成されたと思われます。
さて、お酒はその原料がでんぷん質か糖質かによって、製造方法が変わります。酵母は、糖質であるブドウ糖を資化して炭酸ガスとアルコールを生成しますが、でんぷん質をアルコールに変えることはできません。
米を原料にした酒造りは、奈良時代初期の「大隅国風土記」に登場します。でんぷん質である米に天然の酵母が付着してもお酒にはなりません。でんぷん質である米を糖質に変えるために、当初は口かみという方法を用いました。これは、米を口の中でかむことにより、唾液に含まれるアミラーゼという酵素がでんぷんをブドウ糖に分解します。多くの人で米をかみ、それを容器に戻すことで天然の酵母が付着し、アルコールが生成されたと思われます。また、同時期には、米が水に濡れてカビが生え酒になったという記述もあります。


平安時代中期に書かれた「延喜式」では、現在の酒造りの原型となっている記述が散見されます。例えば、「諸白(もろはく)」といって、麹米と掛米の両方を精米して透明度の高い酒を造った、あるいは「菩提元(ぼだいもと)」という現在の酒母にあたるものが造られたことが書かれています。
室町時代になると酒造りは急速に進歩し、1500年頃には、現在の酒造りの基礎ができました。「三段仕込み」、「火入れ」、「ろ過」など現在の酒造りにとって欠かせない工程はすでにこの頃から行われています。フランスの細菌学者パスツールは、1865年にワインの腐食防止のため「低温殺菌法」を開発しましたが、わが国ではそれより300年前からこれと同様の意味をもつ「火入れ」が行われていたのです。
中世、近世を経て酒造技術も徐々に進歩し、江戸時代、明治時代には、酒の生産量、消費量が大幅に増加したため、明治時代には、酒税を重くすることで国家歳入の3割ほどを酒税で確保しました。ところが、当時の酒造りは大幅に進歩したとはいえ、酒蔵や自然界に存在するいわゆる「蔵付き酵母」に頼っていたため、年によって酒質が安定せず、場合によっては腐造という状態に陥り、もろみが腐るということがたびたび起こりました。
国家の財源である酒税を確保するには、もろみを健全に発酵させることが不可欠であるため、1904年に大蔵省管轄下に醸造試験所(現在の酒類総合研究所)が設立されました。ここでは、山廃酒母や速醸酒母などが開発され、灘や伏見等の酒造場から優良な酵母が分離され、純粋培養された優良酵母が全国の酒蔵に頒布されるようになりました。これにより再現性のある酒造りができるようになり、日本酒の品質も格段に向上しました。
現代の酒造りは、約500年前の室町時代の酒造りと基本的には変わっておりません。生産される日本酒の多くは古来の製法で造られていますが、一方で多種多様な日本酒が登場しております。
30年ほど前までは酒造りの担い手の多くは、冬季に出稼ぎとして従事する杜氏集団でしたが、杜氏の高齢化や出稼ぎ自体が廃れていることもあり、酒造りの担い手は社員や蔵元に移行しております。以前は女人禁制といって女性が酒蔵に入ることさえできませんでしたが、女性が杜氏や蔵人になっている酒蔵もたくさんあります。こうした女性の感性を活かし、発泡性の酒や濃醇な甘口の酒、低アルコールの酒等を生産し、従来にない女性の客層を取り込んでいる酒蔵もある一方、奈良時代の菩提酛や蔵付き酵母を用いた原点回帰の酒を造り、左党をうならせている酒蔵もあります。昔から酒屋万流といわれておりますが、今後蔵の個性を発揮した煌めくような酒蔵がますます増えることでしょう。